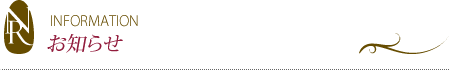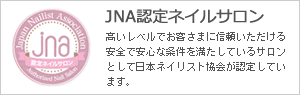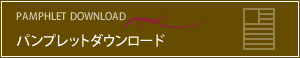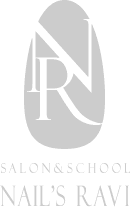皮膚の構造と働きその④【表皮(表皮)※顆粒層(かりゅうそう)〜角層(角層)まで※】
2025/05/30
5月2日の、皮膚の構造と働きその③からの続き・・・基底層➡有棘層ときて、次は【顆粒層(かりゅそう)】です

顆粒層とは、まだぎりぎり細胞が生きていて、『角質になるための準備』をしているところです。
ここは、1~2層の扁平な細胞からなり、セラミド(※1)を合成します。
(※1)セラミドとは、皮膚のバリア機能を維持し、水分保持を助ける脂質です。
顆粒層には他に、【ケラトヒアリン顆粒】という細胞が蓄積されていて、光を屈折させ紫外線が肌深部まで浸透するのを防ぐ役割もしています。
このケラトヒアリン顆粒は、フィラグリン(※2)に分解され、角層の構造を形成していきます。
(※2)フィラグリンとは、角層に存在する天然保湿因子(NMF=Natural Moisturizing Factor)の元となり、肌のバリア機能や水分保持に重要な役割を果たしているタンパク質です。
つまり、顆粒層は、角質細胞になるための準備をするために、皮膚をしっかりと固くし、バリアをつくり、保湿にかかわるタンパク質をつくるなど、角層として外の世界と戦う準備を整える“最終加工工場”のような場所です。
最後に一番外側にあるのが【角層(かくそう)】です。
【角質層(かくしつそう)】とも言いますが、ここでは【角層(かくそう)】と書いていきます。
角層は、皮膚の一番外側にある層で、外からの刺激や菌などから肌を守る「バリア」のような役割を持っています。
角層はすでに死んでいる細胞(角質細胞)が10~20枚ほど重なってできており、体の内側から水分が逃げないように保つ働きもあります。
角層の細胞は、皮膚の内側(基底層)で生まれた細胞が、少しずつ形を変えながら押し上げられ、最終的に死んで角層になります。
これらの細胞はただの「死んだ細胞」ではなく、きちんと働く“鎧(よろい)”のような存在です。
この角層をわかりやすくたとえると、「レンガの壁」に似ています。
レンガが角質細胞、レンガとレンガの間を埋めるモルタルが「セラミド」などの脂(あぶら)です。
この脂が細胞同士をしっかりつなぎ、水分を閉じ込めたり、外の刺激をブロックしたりしています。
また、角層の外側には、汗腺(かんせん)から出る「汗」と、皮脂腺(ひしせん)から分泌される「皮脂(ひし)」が混ざり合ってできた【皮脂膜(ひしまく)】というものがありますが、これはまた今度詳しく書きたいと思います。
さて、角層ですが、ずっと同じ状態ではなく、毎日少しずつ垢となってはがれていき、約28日~45日ほどで新しいものに生まれ変わります(これを「ターンオーバー」といいます)。


角層を大切にすると、肌はなめらかでうるおいのある状態になり、乾燥や肌荒れもしにくくなります。
反対に、角層がダメージを受けると、カサカサしたり、外からの菌が入りやすくなって炎症などのトラブルが起こりやすくなります。
だからこそ、外の世界と戦っている角層の保湿がとても大切です。
ということで、皮膚の構造と働きを4回にわたって書きましたが、伝わったでしょうか?
最後に・・・
表皮のしくみを知ることは、自分の体をいたわる第一歩です。
そして、毎日の正しいケアが、未来の肌を作りますよ。

Salon & School NAIL’S RAVI
長崎市平和町1-9 中和ビル1F シェアサロンアトリエ内